自閉症、ASD等の発達障害解明の研究を行っています。
リニューアル!平成・令和 リレーブログ
津市立病院と当時の女医
2024年11月18日 江藤みちる
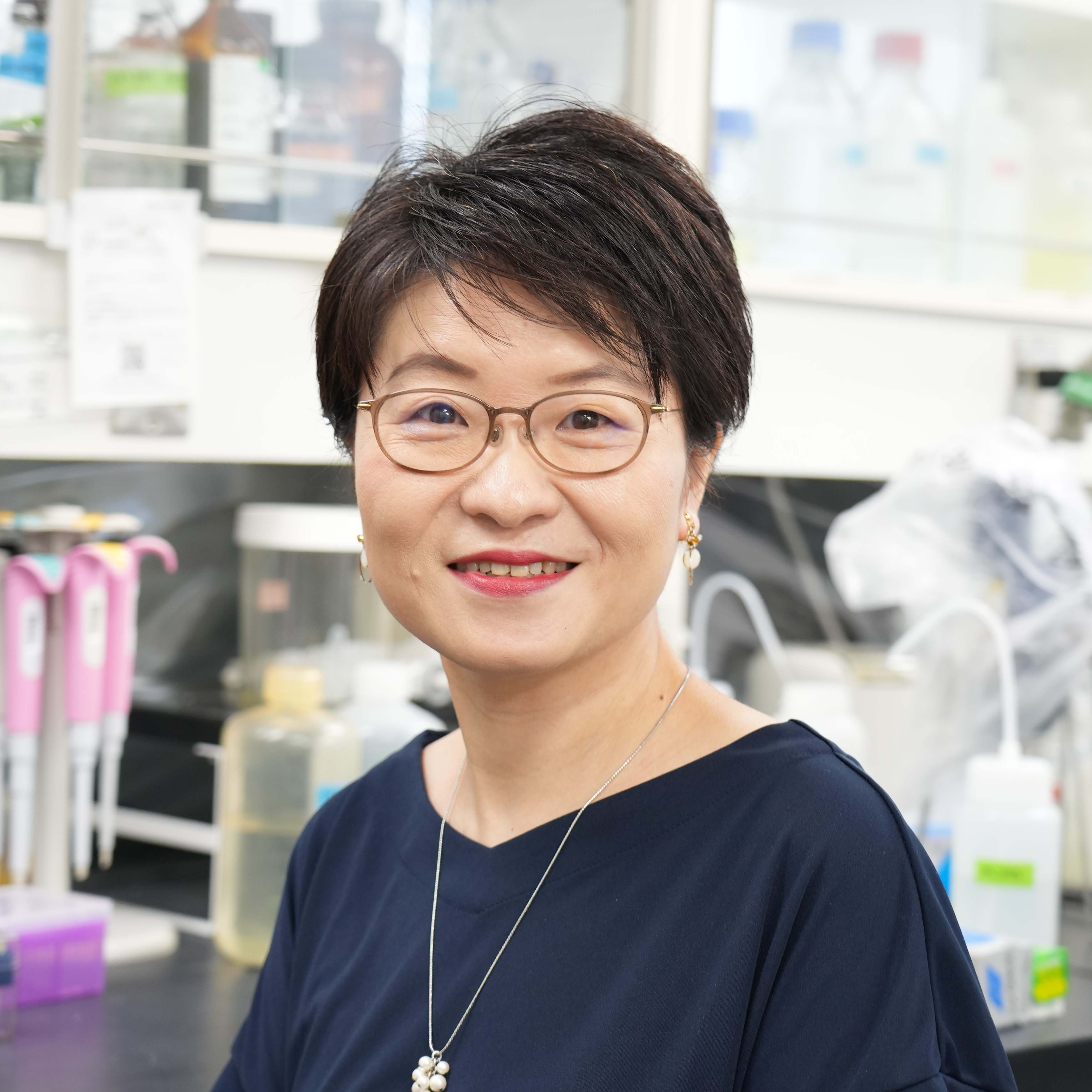
今年、三重大学医学部は創立80周年を迎えました。11月17日には記念式典が三翠ホールにて行われました。
三重大学医学部をご卒業され、世界的にご活躍されている3名の先生方のご講演、いずれも興味深く聞かせていただきました。
式典の冒頭にはご来賓の祝辞がありました。
津市長・前葉泰幸氏のお話の中で、三重大学病院はもともと津市の病院であったことをお話いただきました。
以下、2024年5月1日発行の津市の広報誌「広報つ!」の市長コラムより引用します。
広報つ! 2024年5月1日『明治4(1871)年に津観音境内に設置された官設治療所が前身となり、明治9(1876)年、三重県公立病院が設立されました。2年後、塔世橋のたもとに新院舎が落成し、明治23(1890)年から20年間、私立今井病院として貸与された後、市の公立病院経営に難色を示した医師会との調整を経て、明治43(1910)年に津市に移管されることとなりました。(中略) 昭和19(1944)年、戦時に際して栄町に三重県立医学専門学校が新設されたことに伴い、津市立病院は同附属病院として県に移管され、さらに、昭和48(1973)年からは前年に設置された三重大学医学部の附属病院(三重大病院)として国に移管されて現在に至ります。』
つまり、1876年 三重県の病院として設立→1890年 私立として貸与→1910年 津市に移管→1944年 県に移管→1973年 国に移管、と移り変わってきたのです。
三重大学はもともと三重県立だった、というのはもちろん知っていましたが(古い備品にはいまだに「三重県立大学(医)」と備品シールが貼ってあります)
その前の出来事は今回初めて知りました。
また、2024年5月1日発行の津市の広報誌「広報つ!」の市長コラムには、次のように続いています。
『昭和30年代に遠山病院、岩崎病院、武内病院、永井病院が、昭和50年代には吉田クリニック、津生協病院、大門病院、榊原温泉病院が開設されました。これにより、津市は三重大病院と国立病院機構が運営する三重中央医療センターとともに、地域の中核となる民間病院が数多く存在する、医療体制が充実した都市となりました。』
津市は三重県の県庁所在地であり、中勢地域の中核をなす自治体です。
にもかかわらず、いわゆる市民病院、市立病院は津市には存在しません。
近隣の自治体には、松阪市民病院、亀山市立医療センター、市立伊勢総合病院、市立四日市病院などあります。
津市は中心部に民間病院が多いのと、三重大学病院と三重中央医療センターがあることで、
市の病院を持たずにこれまで医療体制を維持してきたのですね。
また、津市立病院について調べていたところ、
「1927年における津市立病院の女性医師採用」という演題で三重の女性史研究会の佐藤ゆかり氏が発表されていました。
以下、内容を一部引用させていただきます。
『(前略)吉岡が訪問する 4 か月前の 4 月「内科,外科,産婦人科に欠員中だった医員を十八日三名とも女医で補充した,これで各科部長を除く九名の医員中六名まで女医となった」(大阪朝日三重版 1927.4.20)』
『また 10 月には「津市立病院に二十日また一人女医が殖えた,小児科に京大病院から楠谷文子氏が来たので,これで内・外・婦人・小児・眼・耳鼻の六科ともにわたり女医が揃い,婦人科には二人いるから女医は総勢七人,男医は六科長の外には内科に一人ずつ医員がいるだけだから男八人に女七人という陣容である」(大阪朝日三重版 1927.10.26)』
『当時,何故女医を大量採用したのか.(中略)建物の老朽化と改築問題を抱えていた.(中略)女医の大量雇用で人件費の削減を図れたことがうかがえる.また 7 年後の『日本女醫會雑誌』64 号(1934.12)の会員名簿で確認すると,7名のうち5名県外,1名県内郡部で,津市立病院に残った者は1名もいなかった(1 名は不明).様々な見解があろうが,経営側が女医について長期の雇用を視野に入れていなかったとの見方もできる.』
吉岡、というのは吉岡正明のことであり、
東京女子医大の前身である東京女医学校、東京女子医学専門学校の創設者である吉岡彌生の夫の末弟で、
大阪医科大学(阪大医学部の前身)や東京女子医学専門学校の教授をつとめた人物です。
吉岡正明先生は当時、東海地方の病院を視察されました。
津市立病院にいた6名の東京女医学校の卒業生を訪ねてこられた時の記録だそうです。
いまから100年も前に、一時的とはいえ、男性医師8人・女性医師7名=女性医師割合が46.7%、という状況であったことに驚きを隠せません。
一方で、男女の賃金格差はかなり大きく(紡績工で男1円77銭、女1円2銭と、女は男の半分程度しかもらえなかった:佐藤ゆかり氏の論文より)
当時の女医たちはかなり厳しい状況の中で医療に貢献してくださっていたのだと知ることが出来ました。
100年経ち、津市を支える医療はどのように変わってきたでしょうか。
そしてこの先100年、どのように変わっていくのでしょうか。
医師を育て地域に貢献する三重大学医学部の使命を改めて認識した、記念式典の日となりました。
ブログトップに戻る
バナースペース
三重大学 発生再生医学研究分野
〒514-8507
三重県津市江戸橋2-174
TEL 059-232-1111 内線6328
FAX 059-232-8031